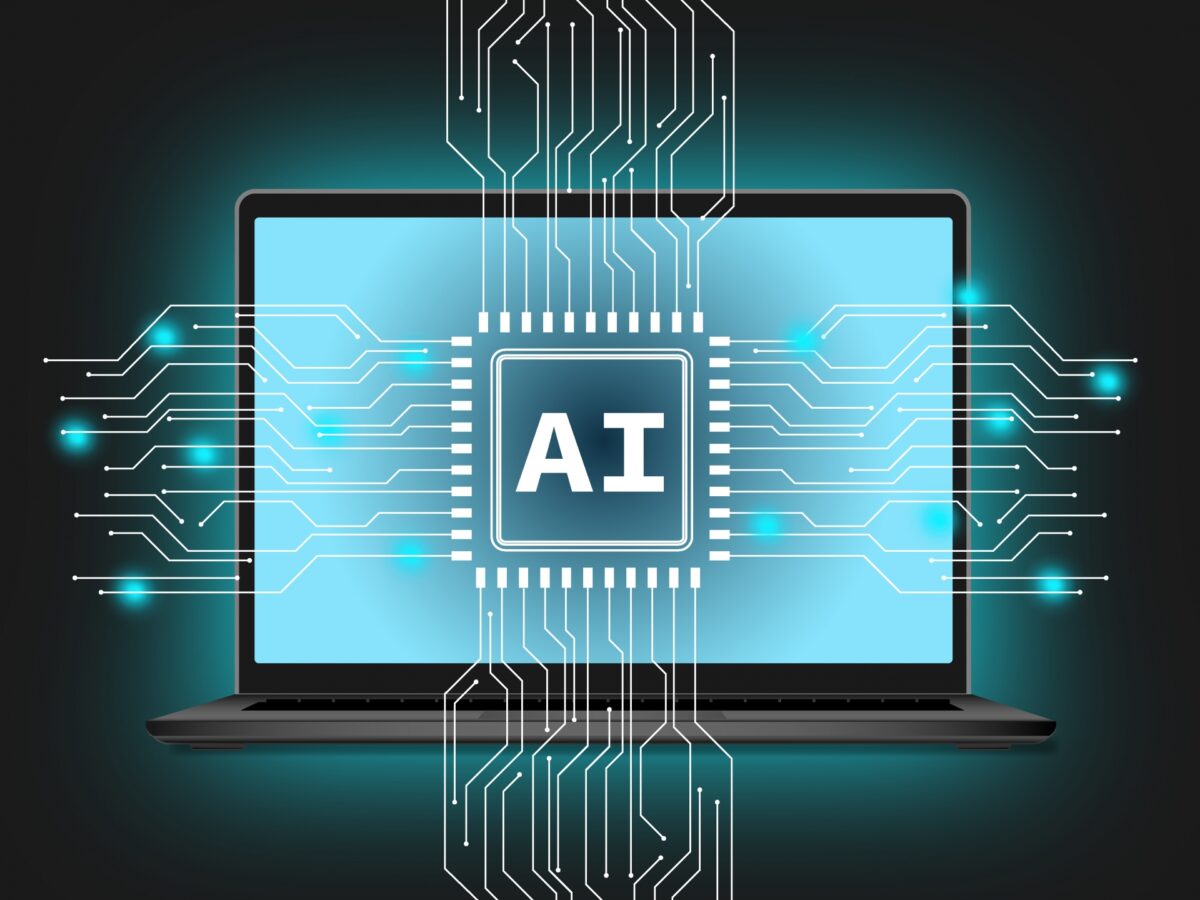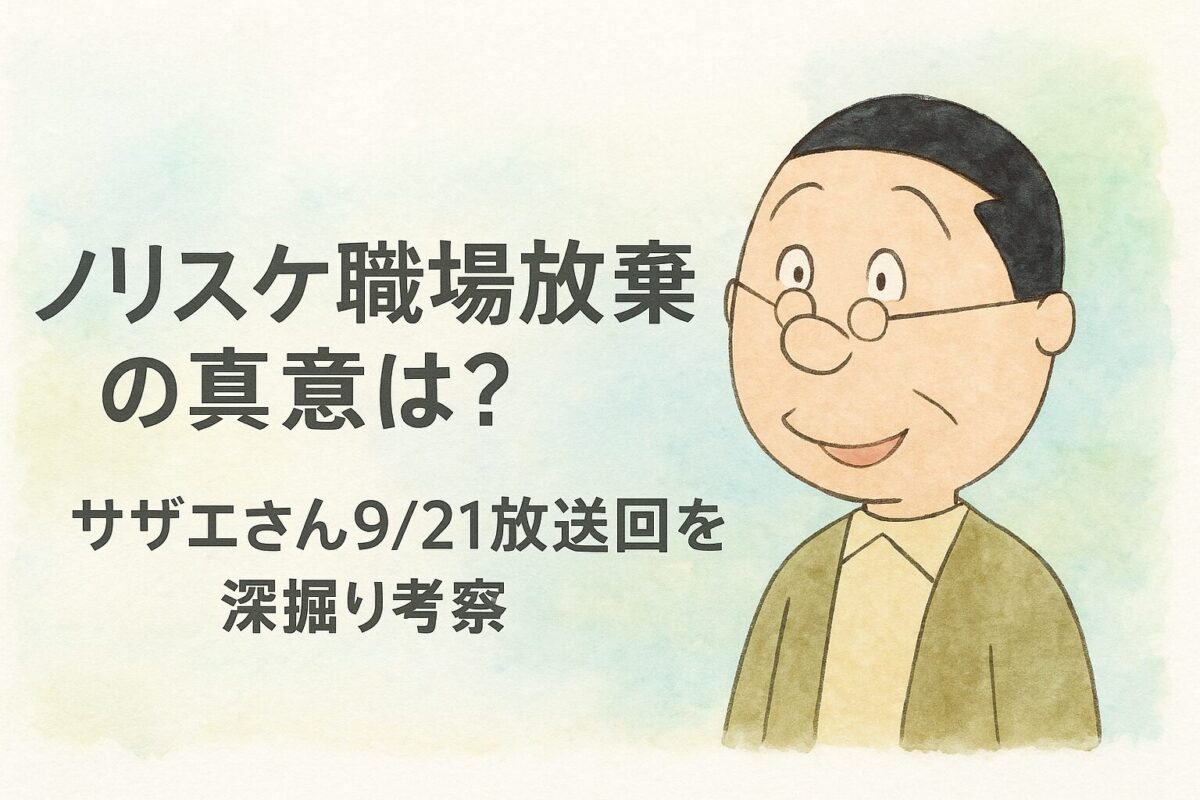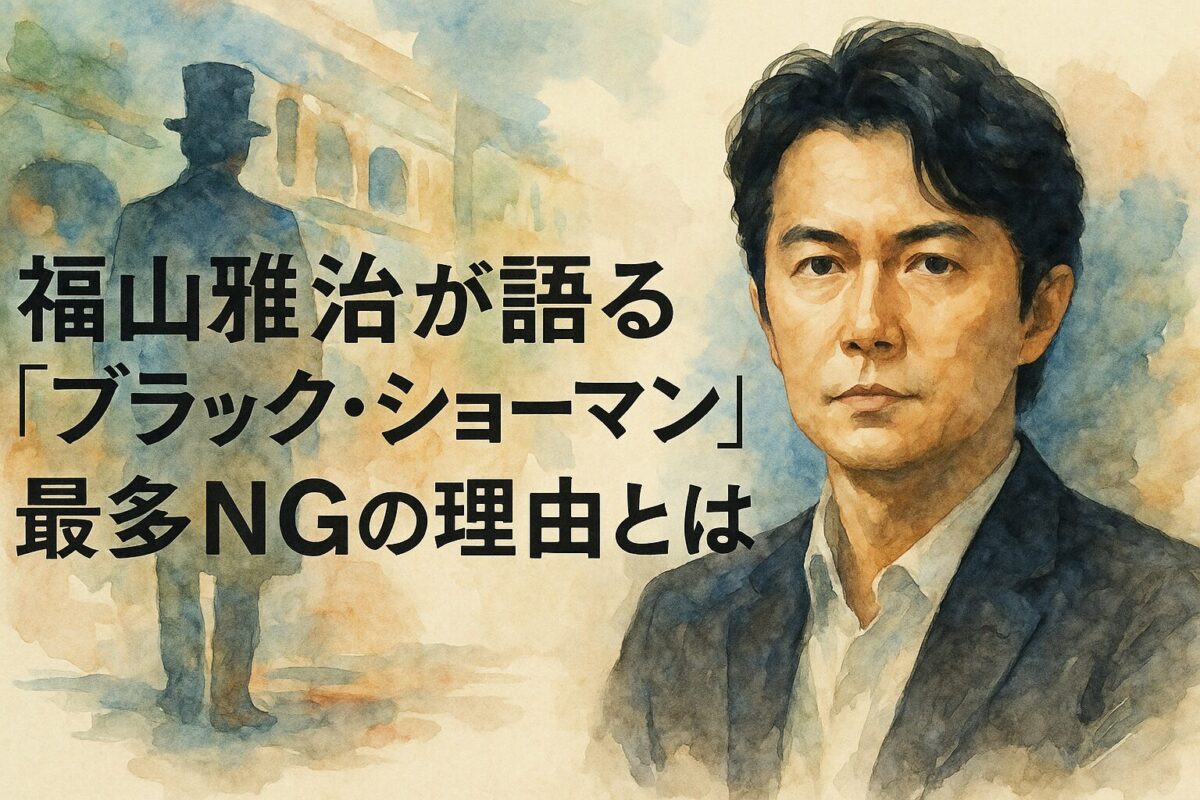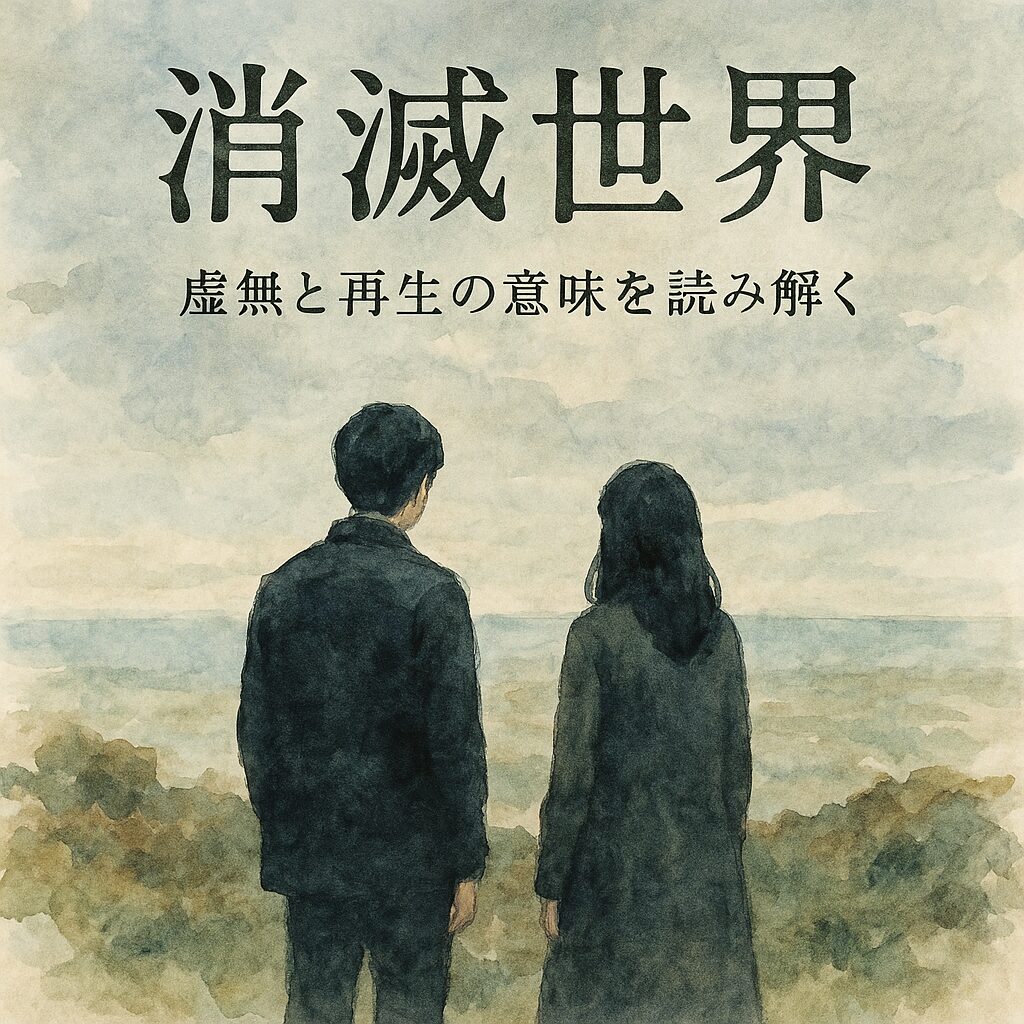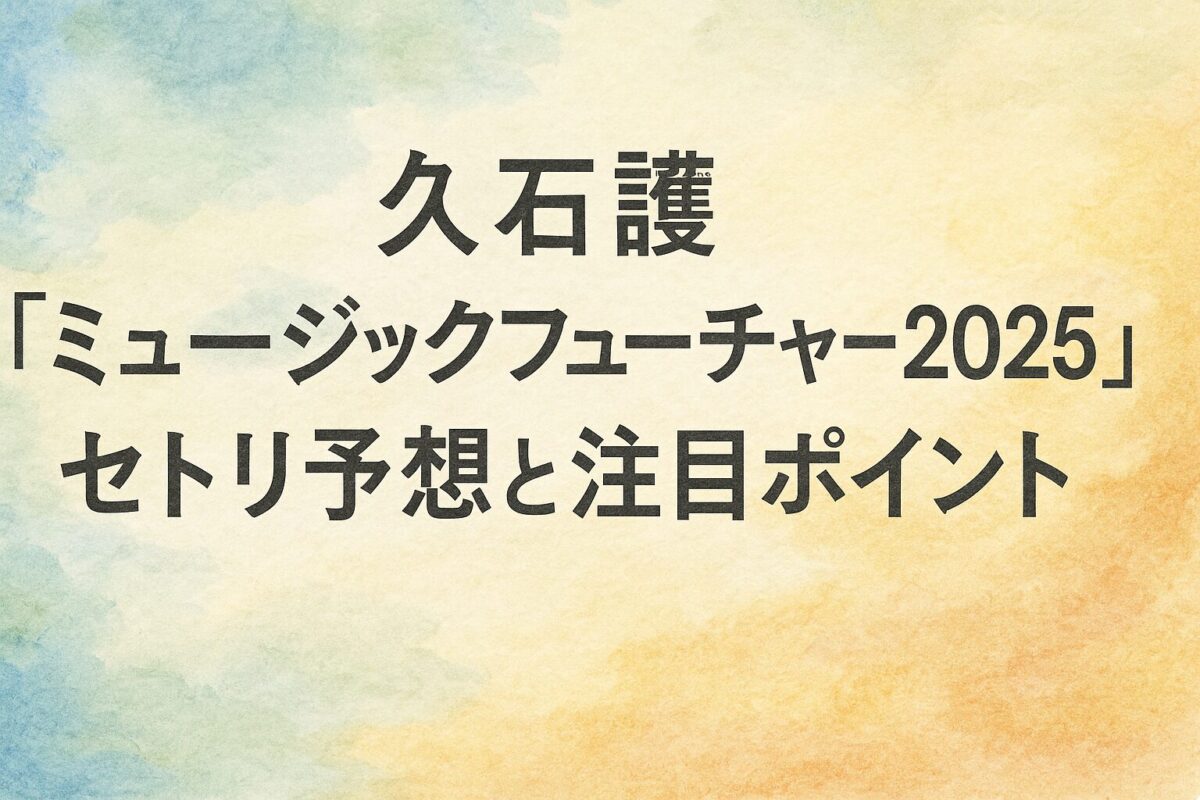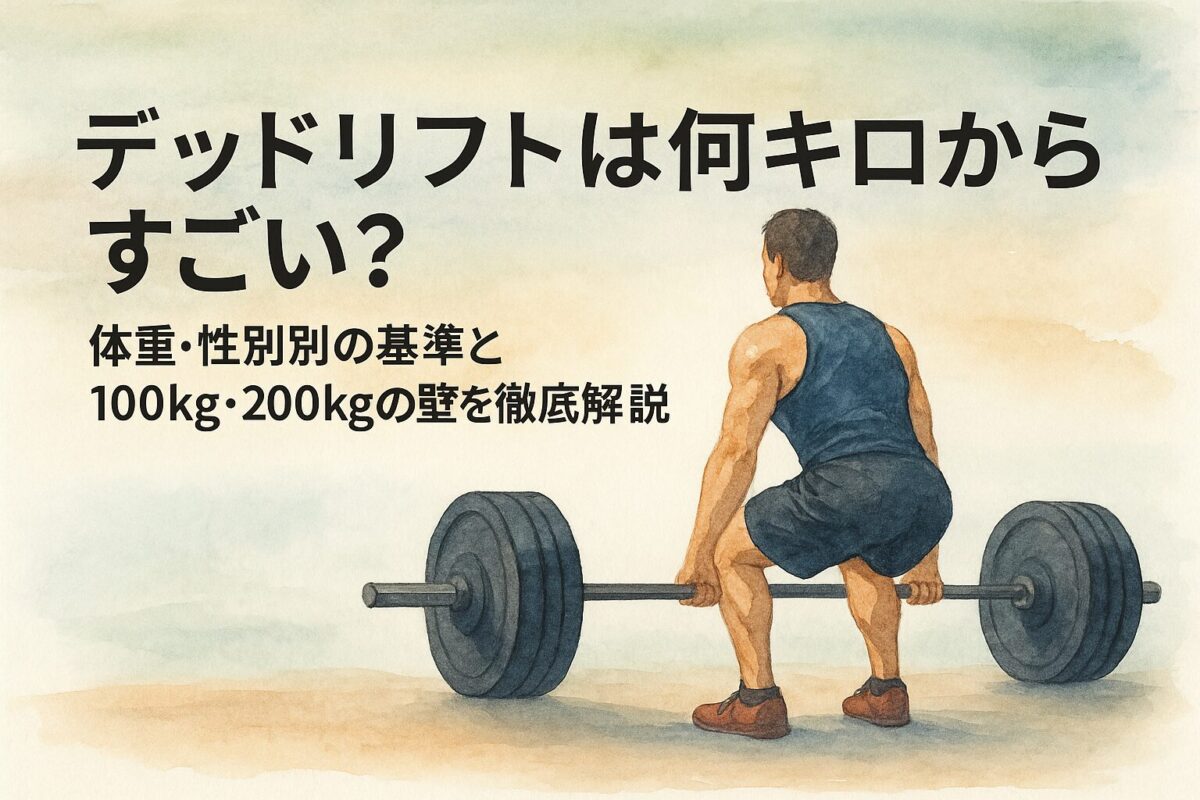「デッドリフトって何キロから“すごい”って言われるの?」と疑問に思ったことはありませんか? ジムでトレーニングを始めたばかりの方や、自分の実力がどのレベルなのかを知りたい方にとって、「どの重量が基準になるのか」は気になるポイントです。
この記事では、複数の信頼性の高いトレーニングメディアをもとに、「デッドリフトは何キロからすごいのか?」を徹底解説します。
体重別・性別の基準はもちろん、100kg・200kgのインパクトや、筋肉の見た目の変化まで具体的に紹介します。
これから本格的に筋トレを頑張りたい方、重量の目標設定に迷っている方にとって、この記事が「強くなるための地図」となるはずです。
デッドリフトは何キロから「すごい」と言われるのか?
一般的な基準は「体重の1.5倍」から
デッドリフトで「すごい」と言われる明確な基準はありませんが、トレーニング界では「体重の1.5倍」が一つの指標とされています。
たとえば、体重70kgの男性であれば、およそ105kgのデッドリフトを挙げることで、周囲から一目置かれるようになるでしょう。
これは、筋トレ経験のある層の中で「中級者」に分類されるレベルです。
つまり、筋トレ初心者の域を脱し、基礎筋力が備わり始めた証でもあります。
そのため、まずは体重の1.5倍を目指すことが、デッドリフトで「すごい」と言われる第一歩となるのです。
しかし、体重が軽い人ほど相対的に難易度が上がるため、単純な重量だけではなく「比率」が重要だということを忘れてはいけません。
100kgを超えると“見た目にもすごい”と感じられる
実際の現場では「100kgを超えたらすごい」という印象を持つ人が多く存在します。
たとえば、フィットネスジムに通っている男性の中でも、100kgを挙げられる人は約25%ほどだというデータもあり、それだけ希少性があることがわかります。
この重量を挙げると、背中や下半身の筋肉も明確に発達してきて、見た目の変化にも現れ始めます。
広背筋や大臀筋が張り出し、Tシャツ姿でも“鍛えている感”が出るようになります。
特に女性で100kgを挙げられる人は非常に少数で、体重60kgの女性が100kgを扱えた場合は、周囲から驚かれるほどのレベルです。
200kgは“上級者・エリート”の証
一方、200kgを挙げるとなると、それはもう「ガチトレーニー」「パワーリフター」クラスの領域です。
体重80kgの男性が200kgを持ち上げるというのは、体重の2.5倍に相当し、一般的なジムの利用者で達成している人はごくわずかです。
200kgを達成するためには、正確なフォーム、筋力だけでなく、可動域、握力、柔軟性、神経系の発達など、総合的な身体能力が求められます。
特に脊柱起立筋、大臀筋、ハムストリングなどの体幹〜下半身の筋力が大きく物を言います。
つまり、200kgという数値は「すごい」の中でも別格であり、誰でもたどり着けるわけではない、高いハードルだと言えるでしょう。
男女別・体重別の“すごい”基準一覧表と読み解き
男性の体重別デッドリフト基準と平均
男性の場合、デッドリフトの「すごさ」は体重との比率で評価されるのが一般的です。
多くのフィットネスメディアやトレーナーの意見を総合すると、以下のような基準が定着しています。
たとえば、体重70kgの男性では、初心者は70kg、中級者は105kg、上級者は140kg、エリートは175kg以上が目安とされます。
以下は「体重×○倍」を基準にした簡易表です(1RM=1回限界):
60kgの人: ・初心者:60kg ・中級者:90kg ・上級者:120kg ・エリート:150kg
80kgの人: ・初心者:80kg ・中級者:120kg ・上級者:160kg ・エリート:200kg
体重が重くなるにつれて必要な重量も比例して上がりますが、体格に応じた負荷でトレーニングすることで、無理なく成長していけます。
女性の体重別デッドリフト基準と評価
女性の場合、筋肉量や骨格の差から、やや異なる基準が設けられています。
目安としては、体重の0.6倍が初心者、1.0倍が中級者、1.5倍が上級者、2.0倍でエリートレベルとされています。
たとえば体重50kgの女性であれば、初心者30kg、中級者50kg、上級者75kg、エリートは100kgです。
以下は女性向けの簡易表です:
45kgの人: ・初心者:27kg ・中級者:45kg ・上級者:68kg ・エリート:90kg
60kgの人: ・初心者:36kg ・中級者:60kg ・上級者:90kg ・エリート:120kg
特に体重50kg未満の女性が100kg以上を持ち上げるのは、非常にレアかつ驚異的なレベルで、競技者・選手クラスと言っても過言ではありません。
偏差値や上位率から見た「すごさ」の指標
筋トレ界隈では、デッドリフトの実力を「偏差値」や「上位◯%」という形で評価する考え方もあります。
あるサイトのデータでは、男性体重80kgで183kgを挙げると偏差値62.5、これは「ジム常連の中でもかなり上位」クラスとされています。
また、体重70kgで163kg(偏差値62.5)は、同体重帯の中でトップ20%前後に入る実力です。
このように、偏差値や上位率で見ると、自分の立ち位置や伸びしろがより明確になります。
つまり、デッドリフトで「すごい」と言われるには、単に数字だけでなく、体格・性別・競技人口の中での相対評価を知ることが重要です。
100kg・140kg・200kgの壁と“見た目の変化”
100kg:初心者卒業レベルと体つきの変化
デッドリフトで100kgを超えられるようになると、多くの人が「初心者を卒業した」と感じられるようになります。
この段階では筋トレ歴6か月〜1年程度の人が多く、背中・腰・脚の筋肉がバランスよく発達してくる頃です。
特に変化が出やすいのは広背筋と大臀筋。
トレーニングウェアやTシャツの上からでも、背中に「厚み」が出始め、姿勢も改善されていきます。
また、腰周りが安定してくるため、ベンチプレスやスクワットにも好影響が出るなど、100kgの達成は“全身強化の分岐点”と言えるでしょう。
140kg:中級者と上級者の分岐点
140kgの重量を扱えるようになると、筋トレ中級者の中でも“頭ひとつ抜けた存在”になります。
このレベルでは脊柱起立筋や僧帽筋、ハムストリングスが著しく発達し、逆三角形のシルエットがより際立ってきます。
また、腰のくびれと背中の広がりに明確なコントラストが生まれ、いわゆる“フィジーク体型”に近づいていきます。
この頃になると「背中が厚くなったね」と言われる機会も増え、周囲からの評価も一段上がるようになります。
なお、140kg前後の重量を8〜10回こなせるようになってくると、200kgチャレンジも現実味を帯びてくる段階に入ります。
200kg:トップクラスの肉体とインパクト
200kgの壁を超えると、それは「体格」も「技術」も上級者の域です。
この重量を扱える人は、全国規模で見ても数%程度。
一般的なジムではほぼ見かけないレベルになります。
体つきとしては、肩から腰までのラインが極めて分厚くなり、広背筋の張り出し、僧帽筋の隆起、ハムストリングの切れまでが一目で分かるようになります。
スーツを着ても分かるほどの“後ろ姿の存在感”が出てくるのがこのレベルです。
加えて、200kgを挙げるための土台として他の筋群も総動員されるため、ベンチプレスやスクワットの記録も自然に伸びていきます。
単なる見た目だけでなく、「全身のパワーの象徴」としての威圧感が宿るのが200kgの領域です。
年齢別・高校生・社会人の“すごい”の境界線
高校生で100kgを超えると一目置かれる存在に
高校生の筋力レベルでは、デッドリフト100kgを達成すること自体が「すごい」と言われる大きな指標になります。
特に体重60〜70kgの高校生であれば、100kgは体重の1.5倍に相当し、筋トレ経験が浅い中ではかなりのハードルです。
実際、トレーニング部や運動部に所属していても、100kgを超える重量を扱える高校生はそう多くはありません。
そのため、学校内のウエイトトレーニング場では目立つ存在になりやすく、フィジカルの自信にも直結します。
また、正しいフォームと計画的なトレーニングをすれば、18歳前後でも120〜140kgまで伸ばすことも可能です。
大学生・社会人:140kg以上が“ガチ勢”の目安
大学生や社会人になると、トレーニングの自由度が増し、ジム通いの頻度や器具の選択肢も広がっていきます。
この層で「すごい」と見なされるのは、おおむね140kgを超えたあたりからです。
特に体重70kg〜80kg前後の成人男性が、1.8倍〜2倍となる重量を挙げられると、明らかにフィジークやパワーリフティングに本腰を入れている印象を与えます。
大学の体育会系であれば150kg超えはさほど珍しくないですが、一般のフィットネスジムでは圧倒的に少数派です。
つまり、社会人でも140kgを越えてくると“上位トレーニー”として扱われるのは間違いありません。
40代以降でも100kgは“維持と成長”の証
年齢が上がるほど、筋力の維持・向上には工夫と継続が不可欠になります。
40代〜50代であっても、正しく鍛えていれば100kgを挙げることは十分可能であり、それは周囲から「すごい」と評価されるだけでなく、健康的な身体の象徴とも言えます。
また、デッドリフトは代謝を大きく上げる全身運動であるため、中年層においても姿勢改善・腰痛予防・脂肪燃焼に直結する効果があります。
年齢を重ねても継続して100kgを扱えている人は、単なる筋力以上に「身体管理能力の高さ」が光る存在です。
そのため、「年齢に見合わぬ動きと見た目」を実現できるのが、デッドリフト継続者の特権なのです。
200kgを目指すためのトレーニング計画と注意点
ステップ①:まずはフォームを極めることが最優先
200kgという重量は、ただ力任せに引けるものではありません。
最初のステップとして重要なのが、フォームの習得と安定性の確保です。
正しいデッドリフトフォームは、背中を丸めず、股関節主導で引き上げる動作を徹底します。
また、スタートポジションでの足幅やバーとの距離、握り幅なども細かく調整し、自分の骨格に最も適した動きを身につける必要があります。
この段階では、MAX重量の60〜70%程度(例:140kgの人なら90kg〜100kg)で、8〜10回を3セット行うことが理想です。
回数を通じて動作の癖を修正し、神経系と可動域の強化を目指します。
ステップ②:週単位の漸進型プログラムで重量UP
中級者を抜け出し、200kgを目指すには“段階的に重量を増やしていくプログラム”が欠かせません。
一般的には8〜12週間で構成された「ピリオダイゼーション(周期化)」を用いるのが効果的です。
例としては以下のようなスケジュールが推奨されます:
・1〜4週目:70%(8回3セット) ・5〜8週目:80%(5回5セット) ・9〜10週目:90%(3回×2セット) ・11週目:95%(1回1セット) ・12週目:MAX挑戦
このように回数と重量を逆相関させながら段階的に強化することで、フォームを維持したままパワーを伸ばすことができます。
注意点:握力・体幹・回復が伸び悩みのカギ
200kgの壁で最もつまずきやすいポイントが「握力」と「体幹の安定性」です。
特にストラップを使わずに高重量を扱うには、前腕の筋持久力が不可欠となります。
このため、補助種目として懸垂やリストカールを取り入れることで、握力強化も同時に進めることが重要です。
また、重たいデッドリフトは中枢神経への負担も大きく、オーバートレーニングに陥りやすい種目です。
1週間に2回以上行う場合は、日を空け、部位分け・休息・栄養補給を意識して回復を最優先に計画を立てましょう。
コンディションを整えることが、200kg突破の最大のカギになります。
まとめ:デッドリフトは“体重×○倍”がすごさの目安
何キロから“すごい”かは、体重と性別で変わる
デッドリフトで「すごい」と言われる基準は、単なる重量ではなく、体重とのバランスが重要です。
一般的に、男性であれば「体重の1.5倍」、女性であれば「体重と同じ重量」が中級者ライン、これを超えると周囲から一目置かれるようになります。
また、100kg・140kg・200kgといった重量の節目では、筋肉の見た目やフィジカルの印象も大きく変化し、それぞれに達成感と自信が伴います。
目標を明確にすれば、成長は加速する
多くの人がデッドリフトの重量アップに苦戦する理由は、「具体的な目標設定」がないからです。
今回紹介した体重別・年齢別の基準表を活用することで、現状を把握し、自分の次のステージを明確に描くことができます。
まずは“体重の1.5倍”を目指し、フォームと土台を固めたうえで、次は“2倍超え”という上級者の壁に挑んでいきましょう。
無理せず、継続と計画が成果を生む
デッドリフトは、高重量に挑むほどリスクと効果が表裏一体になります。
握力・回復・フォームなど、1つでも欠けるとケガや停滞の原因になりかねません。
そのためには、定期的なフォーム確認や、ピリオダイゼーションに基づいた重量設定、必要に応じた休息と栄養管理が不可欠です。
あなたの現在地と目標を明確にして、無理なく継続することで、やがて200kgも現実になります。
さあ、あなたも次に「すごい」と言われるのは、自分だと信じて今日から1kgずつ伸ばしていきましょう。